2025年7月18日公開(2025年7月18日更新)
代位弁済とは?仕組みや返済の流れ、リスクや対処法をわかりやすく解説
#金融
#返済
2025年7月18日時点の情報となります。
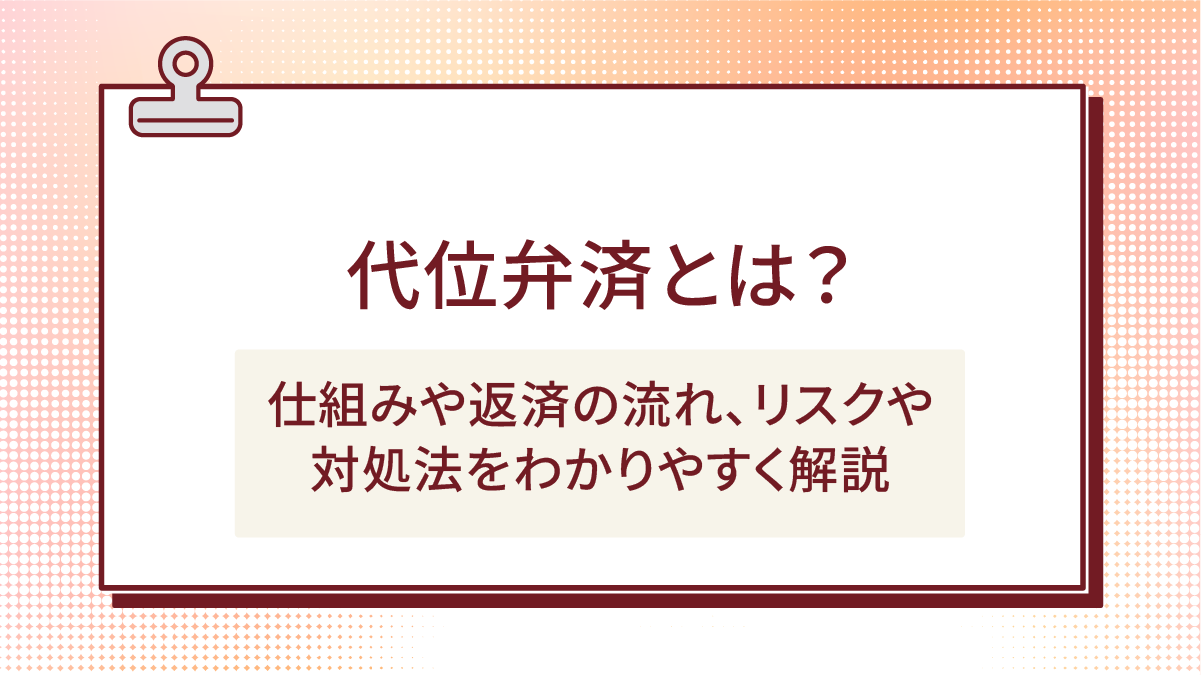

■ Profile
荒木 和音(あらき かずね)
保険代理店での個人向け家計相談や企業のリスクコンサルティングを経て、金融専門ライターとして独立。現在はWEBメディアを中心に、クレジットカードやカードローン、資産運用などに関する記事を幅広く執筆している。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。
住宅ローンやカードローンなどを活用していると、「代位弁済」という言葉を目にする機会があるかもしれません。
代位弁済とは、借主が何らかの理由で返済できなくなった場合に、保証会社などの第三者が代わりに金融機関へ返済を行う制度です。しかし、代位弁済が実行されるとさまざまなデメリットが生じる可能性があるため、計画的に借り入れや返済を行う必要があります。
本記事では、代位弁済の基本的な仕組みやリスク、実際に代位弁済の通知が来た場合の対処法などを解説します。
1. 代位弁済とは
代位弁済とは、ローンの返済などが滞ってしまった場合に借主に代わって第三者が債務を返済する制度です。理解を深めるために、まずは基本的な仕組みや関連する法律などをみていきましょう。

1.1 代位弁済の仕組み
代位弁済の仕組みは、借主に代わり、保証会社などの第三者が、金融機関などの貸主に対して残っている債務を一括で返済するものです。これにより、貸主は貸し倒れのリスクを回避できます。
ここで注意すべき点は、代位弁済によって借金そのものが消滅するわけではない、という点です。
代位弁済が行われると、もともと貸主が持っていた借金の返済を求める権利(債権)が、返済を肩代わりした保証会社などの第三者に移ります。つまり借主は、その保証会社などの第三者に対して返済を続けていく必要があります。
代位弁済は返済先が変わるだけで、返済義務はなくなりません。また、一括で返済を求められたり、遅延損害金が加算されたりするケースが一般的です。
1.2 誰が支払う?代位弁済の主なケース
代位弁済では一般的に、ローンの契約時に保証契約を結んだ保証会社が代位弁済者となります。
しかし、保証会社だけではなく、連帯保証人が代位弁済者になるケースもあります。連帯保証人とは、借主が返済できなくなった場合に借主と同等の返済義務を負う人を指します。
1.3 代位弁済に関する民法の内容
代位弁済は、私たちの生活に関わる法律である民法にも規定されています。代位弁済に直接関連する民法の主な条文には以下のようなものがあります。
この条文は、借主本人でなくても第三者が代わりに弁済(返済)できることを定めています。代位弁済の基本的な根拠の一つです。
この条文は、借主のために弁済した第三者(保証会社など)が元の債権者(金融機関など)の地位を引き継ぐ(代位する)ことを定めています。
この条文は、債権が譲渡された場合の通知や承諾に関するルール(民法第467条)が一定の条件の下で代位弁済にも適用されることや、弁済について正当な利益を持つ者(保証人など)が代位する場合には、債務者への通知や承諾がなくても代位の効果が生じることを示しています。
2. 代位弁済と第三者弁済の違い
代位弁済と似た言葉に、「第三者弁済」があります。どちらも第三者が債務を弁済する点は共通していますが、両者には明確な違いがあります。
たとえば、親が子の借金を肩代わりして返済するようなケースは第三者弁済にあたりますが、ここでの第三者は法律上の利害関係を有していないため、原則として弁済した第三者に債権は移転しません。つまり、親が借主である子に対して法的に返済を請求する権利を得られるわけではないということです。
一方、代位弁済は、弁済した第三者(保証会社など)に債権が移転します。そのため、第三者は法律上、当然に借主に対して返済を求めることが可能となります。
ただし、第三者弁済において債権者から債務者に対する通知、または債務者の承諾があった場合、第三者は借主に対して返済を要求できます。
3. 代位弁済が行われる際の一般的な流れ
実際にローンの返済が滞った場合、代位弁済はどのような流れで進むのでしょうか。ここでは、一般的な流れを3つのステップに分けて解説します。
ただし、金融機関や契約内容によって流れは異なる場合があるため、あくまで目安として参考にしてください。
3.1 【1】返済が滞ると貸主から督促を受ける
借主が決められた返済日に支払いを怠った場合、まず貸主である金融機関などから電話や郵便で返済を促す連絡が来ます。この段階で速やかに返済を行えば、代位弁済に至ることはありません。
しかし、督促があっても返済が確認できない状況が続くと、貸主はより厳しい対応を取るようになります。内容証明郵便で、代位弁済予告通知や催告書といった書面が送られてくることもあります。これは、このまま返済がない場合は保証会社による代位弁済の手続きに入るという最終通告のようなものです。
金融機関によって異なりますが、一般的には返済の遅延が3ヵ月前後続くと、代位弁済の手続きが開始されます。
3.2 【2】保証会社が貸主に代位弁済を行う
貸主からの督促を受けても返済がない場合は、保証会社が借主に代わって貸主へ残債務を一括で弁済する、代位弁済が行われます。
代位弁済が実行されると、借主に対して、保証会社が支払った金額や債権が保証会社に移った旨が記載された代位弁済通知が送付されます。
3.3 【3】保証会社が借主に返済請求を行う
代位弁済によって債権が保証会社に移行すると、それ以降は保証会社が新たな債権者となり、借主に対して返済を求めることができます。
4. 代位弁済のリスクや影響
代位弁済が行われると、以下のようなデメリットを被る可能性があります。
- 一括返済を求められる
- 遅延損害金の支払いが発生する
- 保証人に対して督促が行われる
- 信用情報に問題が記録される
- 財産の差し押さえが行われる
どのようなリスクがあるのかを理解し、返済が滞らないよう注意しましょう。
4.1 一括返済を求められる
保証会社は、借主に代わって金融機関へ債務を一括で支払っています。そのため、保証会社は借主に対し、その弁済額(元金、利息、代位弁済までの遅延損害金などを含む全額)を一括で返済するよう要求するのが一般的です。
月々の分割返済が困難になった結果として代位弁済に至っているケースがほとんどであるため、この一括請求に応じるのはむずかしい場合が多いでしょう。保証会社からの支払請求に応じず放置した場合、保証会社は支払督促や訴訟といった法的手続きに進む可能性が高くなります。
4.2 遅延損害金の支払いが発生する
借り入れの返済が遅れた場合は、通常の利息とは別に遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は通常の貸付利率よりも高く設定されていることが多く、返済総額がさらに増してしまう恐れがあります。
代位弁済が実行されるケースでは、すでに返済が長期間滞っている状態であるため、遅延損害金も積み重なっていることが多いでしょう。代位弁済後は保証会社に対して返済義務を負うことになりますが、ここでも返済が遅れれば、遅延損害金が新たに発生します。
遅延損害金の一般的な計算式は以下のとおりです。
たとえば、借入残高が300万円、遅延損害金年率が20.0%、遅延日数が90日(約3ヵ月)の場合、約14万7,945円(=300万円×0.20÷365日×90)の遅延損害金が発生する計算になります。
4.3 保証人に対して督促が行われる
代位弁済が実行されると連帯保証人に対しても督促が行われるため、負担をかけてしまう恐れがあります。
代位弁済が行われると、保証会社は借主だけでなく連帯保証人に対しても返済を請求できます。連帯保証人は、借主が返済できない場合、代わりに返済する義務を負っているためです。
借主が返済をしなければ、連帯保証人にも負担がかかってしまい、人間関係にも影響をおよぼす恐れがあります。
4.4 信用情報に問題が記録される
信用情報とは、ローンやクレジットカードの申し込みや契約、支払い状況などに関する個人情報のことです。信用情報はCICやJICCなどの信用情報機関によって管理されており、金融機関が融資の審査などを行う際に参照されます。
代位弁済が行われると、その事実は事故情報として信用情報機関に一定期間登録されます。事故情報が登録されると、新規のローンの審査に通りにくくなったり、新たなクレジットカードの作成がむずかしくなったりするなど、日常生活に悪影響をおよぼす場合があります。
4.5 財産の差し押さえが行われる
保証会社からの一括請求に応じず連絡も取らないなどの不誠実な対応を続けると、保証会社は債権回収のために法的措置をとることがあります。裁判所が保証会社の主張を認めた場合は強制執行の申し立てが可能となり、給与や預貯金、不動産といった財産が差し押さえられるリスクがあります。
5. 代位弁済の通知が来たときの対処法
実際に代位弁済の通知が来たときは放置せず、冷静に対処しましょう。
もし資金的な余裕があり、一括での返済が可能な場合は、速やかに応じるのが最もよい解決策です。一括での返済がむずかしい場合でも、まずは保証会社に連絡を取り、分割での返済ができないか交渉してみましょう。必ず応じてもらえるとは限りませんが、返済の意思を示すことは重要です。あわせて親族に事情を説明し、資金援助を頼むことも検討してみましょう。
どうしてもお金の工面がむずかしい場合は、保証会社に競売にかけられる前に住宅を任意売却するのも一つの方法です。任意売却の方が競売よりも高値で売れる可能性があり、残債を減らせる可能性があります。
また、返済の目処がまったく立たない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、債務整理を検討するのもよいでしょう。債務整理には主に以下3つの方法があります。
| 任意整理 | 裁判所を通さず、専門家が債権者と交渉し、将来利息のカットや分割払いの期間延長などによって無理のない返済計画を立てる手続き |
|---|---|
| 個人再生 | 裁判所に申し立て、借金の大幅な減額を目指して減額された借金を分割返済する手続き |
| 自己破産 | 裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらい、原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらう手続き |
6. 代位弁済を避けるための返済のポイント
代位弁済は大きなリスクを伴うため、できる限り避けたいものです。ここでは、代位弁済を未然に防ぐための返済のポイントを解説します。
6.1 返済計画を立てて返済を進める
お金を借りる際は事前に返済シミュレーションなどを活用し、毎月の返済額や返済総額、返済期間を具体的に把握しておきましょう。そのうえで、収入や支出のバランスを考えながら、無理のない金額を借り入れます。そうすることで将来的な返済の見通しがつき、安心して返済を進められます。
6.2 返済忘れがないようにする
自分に合った返済方法を選び、返済忘れがないようにしましょう。
金融機関によっても異なりますが、ローンの返済方法は主に以下の3つです。
- 口座引き落とし
- 提携ATM
- インターネットバンキング
複数の金融機関から借り入れがあり返済管理が複雑になっている場合は、おまとめローンの活用を検討するのも一つの方法です。おまとめローンは複数の借り入れを一本化し返済先を一つにまとめることができるローンで、返済の管理がしやすくなると同時に金利負担が軽減される場合もあります。
おまとめローンについては以下の記事でより詳しく解説しています。
>> おまとめローンとは?カードローンにまとめるメリットや注意点をわかりやすく解説
6.3 生活費の見直しを行う
毎月の支出を見直し、無駄な出費を削減することで返済資金を確保できれば、返済が滞ることを防げるでしょう。
まずは家計簿をつけて収支を可視化し、どこに無駄があるのかを把握するのがおすすめです。そのうえで、スマートフォンの料金プランや生命保険料、光熱費など、定期的な支出(固定費)を見直してみましょう。固定費はプラン変更など少ない手間で支出を削減できることが多く、一度見直すと節約効果が長期間続く傾向にあります。
固定費を見直したら、次に食費や交際費のような日々の支出を工夫してみましょう。
収支の見直しについては以下の記事もあわせてご覧ください。
>> 今すぐお金が必要な人必見!すぐに借りる方法・やってはいけないことなどを解説「【お金がない時の対処法1】収支を見直す」
6.4 もしもの場合は早めに貸主へ相談する
病気や失業、収入の減少など、予期せぬ事態で返済がむずかしくなりそうだと感じたら、放置せずにできるだけ早めに貸主に相談しましょう。事前に相談することで、一時的な返済額の減額や返済期間の延長など、何らかの救済措置を検討してもらえる可能性があります。
7. まとめ
代位弁済は借主に代わって保証会社などの第三者が返済を行う制度ですが、借金がなくなるわけではなく、返済先が第三者に変わるだけです。さらに一括返済の請求や遅延損害金の発生など、さまざまなリスクが伴います。
重要なのは、代位弁済に至らないよう計画的な返済を心がけることです。返済計画を立てたうえで借り入れをするだけでなく、ときには生活費を見直すことも考えてみましょう。
どうしても返済がむずかしくなりそうな場合は、早めに貸主や専門家に相談してください。
